
二 密談
花屋の番頭の計らいで、一室に行灯の灯が点り、二人は丁稚が出ていくまで黙ったまま座っていた。
「其角様、一体何の話でしょうか?」
「之道さん、実は芭蕉翁の辞世の句についてなのだが、このまま芭蕉翁が目を覚さずそのままお亡くなりになった場合、辞世の句を持たずに逝ってしまうことになり、芭蕉翁の名声に傷がつくし、我が一門として世間体としては大変悪いことになる」
「確かにそうでございますね。大阪では昨年談林の井原西鶴さんが死んで談林も落ち目となり、いまや我が蕉門が、世間の注目を集めているところでありますから、宗匠の死は大変痛手となりましょう。私は去来様ではなく、其角様が宗匠の亡き後は、この蕉門を率いていくお方と思っております。蕉門の行く末を考えますと真に不都合でございますね」
「しかもじゃ。芭蕉翁の最後の句が貴方も存じている通り『秋深き・・』の句です。このままでは、芭蕉の名にも拘わると思いませんか」
「確かにそうでございますね。私も最近の宗匠の『かるみ』とか申す句風には同意しかねると常々思っておりました」
「そこで、芭蕉翁の辞世の句を私どもで作ってはと思っております。そもそも古来から辞世の歌などとは周りの者が、著名な歌人に頼んで作ってもらったり、後世の人が物語や芝居の為に作ったものなんです。例えば太閤さんの有名な『露と落ち露と消えにしわが身かななにはのことも夢の又夢』も淀さんが頼んで作ってもらったものとかいうじゃありませんか。百姓の小倅で戦々に明け暮れて人を取り込むことには長けていたが、風流の道は、利休居士の教えを受けながら、侘び寂びの世界や仏門の『諸行無常』とは縁の無い人でしたとのことですから。太閤さんでも死は訪れるという無常感を京の僧侶が代作したということですよ。当然石川五右衛門の釜茹の刑の歌などはうそっぱちですよ」
「考えてみるとそうでございますね。歌舞伎や浄瑠璃などで面白可笑しく演じられておりますのでいつのまにか信じてしまいました」
「ところが、去来が大阪へこられたら、辞世の句をでっち上げようとしても、芭蕉翁に忠実な彼のことだから絶対反対するでしょう。また発案が之道さんだとなると酒堂が猛反対しますでしょう。仲を芭蕉翁が取り持ったとはいえ、まだしこりは残っておりますでしょうから」
「左様でございますね。私とて宗匠が中に入っていたからこそ形こそ仲直りをしたまでのこと。そうでなければあんな半人前のやつと一緒にいることさえいやでございますから」
「どうしたものか」
「私に名案がございます。八日の夜の伽の番は弟子の泥舟でございます。やつに言い含めますから、宗匠から辞世の句を聞いたことにしましょう。例え去来様がお着きになられても真夜中に宗匠様より聞いたと申せば何も言われないでしょう」
「ただ問題なのは、芭蕉翁が回復して、これがでっち上げとなると問題となって一門が分裂してしまう」
「診立てた医者の話によると『おこり』がかなり悪く、風邪とかいうものでは無いそうです。もっても四五日と申しておりましたので」
「師匠の回復を願わないのは弟子として不謹慎な思いだが、やむを得ないだろう」
「左様でございますね。そこで辞世の句はどの様にいたしましょうか。季題はやはり『時雨』でしょうか」
「いや確かに、芭蕉翁の代表する句といえば『旅人と我が名呼ばれん初しぐれ』であり、後の世の人も芭蕉といえば『時雨』といわれることになるでしょう。しかし芭蕉翁は常日頃、『私の人生は、旅に明け暮れていたし、西行の様に旅の途中に死にたいものだ。』と言っておられた。季語は、旅の寂しさを現す縁語の『枯野』はどうだろうか」
「よろしいこざいますね。宗匠様の辞世の句として将に相応しい季題でございます」
「うむ…『旅に病み尚駆け巡る夢心』というのはどうでしょう?」
「すばらしい句でございます。宗匠様の昔作られていた句に近い侘び寂びを感じます。」
「では、九日の朝手筈どおり、呑舟に一同の前で言わせてください。なぜ起こさなかったと言われたら、『宗匠が必要は無いと』申されたと言い訳すれば大丈夫だと思いますが」
「承りました」
其角は之道と打ち合わせた後、安心したのか又芭蕉が危篤ということで気疲れしていたのかいつのまにか寝てしまっていた。
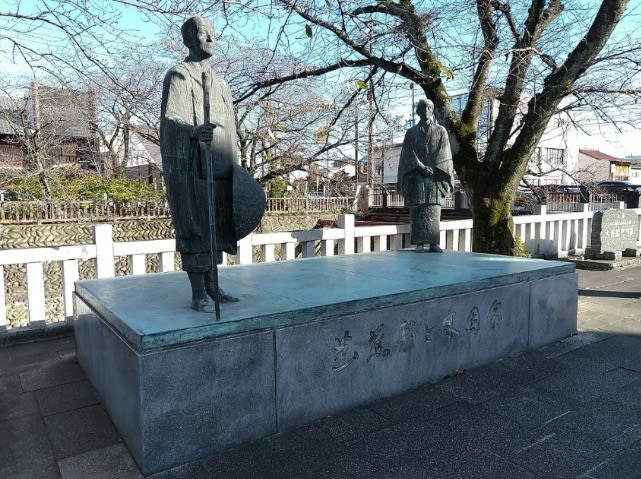
三 異変
次の日は、芭蕉の容態も小康状態を保ち、その日の夜も深けた丑三時に異変が起こった。
どんどんどん。「花屋様。夜分恐れ入ります。京から参りました去来でございます。芭蕉翁のお見舞いとして馳せ参じました。木戸を開けてくださいませ」
「ただいま開けますので。早飛脚を頼んでからまだ日がたたないのですが…」番頭は、目をこすり、去来が来るのがあまりにも早いので、驚きながら木戸を開けた。
「芭蕉翁の一大事ということで、京より淀川を夜通し下って参りました」
騒ぎに、之道がまず目を覚まし、去来が着いたことを知り、急いで其角を起こした。
「其角様、起きてくださいませ。京より去来様がお着きになられました。あの件はいかがいたしましょうか」
「なに去来が…。それはまずいこととなった。打ち合わせたことはしばらく延期しよう」
「それがよろしいですね」
其角は、夜通し淀川を下ってきた去来を迎えた。しばらく芭蕉の病状などを説明して、
「去来どの。今日のところは長旅で疲れたことと存じますので、花屋さんが布団を用意しますので、お休みになられたらいかがでしょうか」
「いやいや其角師匠。芭蕉翁のことが心配ですので、寝ずに起きて看病しております」
「あまり無理をなさらないように」仁佐衛門は去来の決意を知って言った。
去来はずっと起きているつもりだったが、さすがに京から大阪への移動に疲れ、いつのまにか寝ていた。次の日も昼近くになって、去来は起きだし、ばつが悪そうに之道に、
「ついうっかり寝てしまって、申し訳ございません。ところで芭蕉翁の御様子はいかがですか」
「夜通し淀川を下ってきたのですから、しょうがないですよ。去来様のご気分はいかがですか。宗匠は、相変わらず目を覚まさない状態です」
「そうですか。ところで、芭蕉翁の快癒を祈願するには、大阪ではどちらがよろしいでしょうか。私は京の人間なので、こちらの様子はまったく存じ上げないのでお教えてください。」
「それでしたら住吉神社がよろしかと。歌の神さんですし、大阪では一番ご利益がありますよ。私の親戚が病気になり、その奥方が祈願したところ、病も癒え、大変感謝して夫婦ともども鳥居を奉納したということです。それで、去来様がご祈祷にいかれるのですか」
「いいえ。私は、芭蕉翁のそばで看病いたしたいと思いますので、どなたか私どもの変わりに翁の御病気御回復祈願の代参をお願いできないでしょうか。ついでに病魔退散のお守りでも買ってきていただければと思うのですが」
「わかりました。私の店のものをやりましょう。病魔退散の祈祷もお願いしておきますよ」之道が答えた。
「もうしわけございません。」去来は、ひとつ安心した顔で仁左衛門のところへ看病の手筈を相談に行った。
その日の午後になって、乙州、丈艸、木節、正秀がそれぞれ近江から駆けつけた。医者でもある木節は、芭蕉を診ると暗い顔つきとなった。
「もっても四五日かと。何とか薬で持ちこたえているところです。師匠の病状をお聞きすると病名は『おこり』と思われるのですが、この病気は厄介で、師匠のお年を考えると難しい状況にあると申し上げます」
「うむ。やはりそんなに悪いのですか」乙州は、いよいよとの覚悟を決めた。
その次の日の夜になって奇跡が起きた。
突然芭蕉の目が開いのた。
「宗匠様」
「支考か…。何日ぐらい寝ていた?」
「四日ぐらいです。今日は九日の夜明け前です。今大阪の方々、去来様、乙州様らが駆けつけております。今呼んで参ります」
「いや真夜中でもあるし、わざわざ起こす必要もないだろう。それより支考に頼みがある」
「なんでございましょうか?」
「京の嵯峨で吟じた『大井川』の句を覚えているか?」
「はい。『大井川浪に塵なし夏の月』でございますね」
「うむ。それなんじゃが、浪に塵なしとはではちとおかしいので、『清滝や波に散り
込む青松葉』に替えてくれ。う…。塵芥の塵ではなく、花が散るの散るじゃぞ」
「大丈夫でございますか。お休み下さいませ」
「わかった。ただ、どうしても替えて欲しかったものでな」
「承りました」
次の日になって、この一件を一同に告げると。
「どうして起こしてくれなかった。他には芭蕉翁は申してなかったか」
其角は、辞世の句を言ってくれなかったかどうかが心配となったが、改案ということで、
「翁はさすが、病中であっても俳句のことを考えている。まずは安心。しかし改案では困るな。次起きたときには、辞世の句を作ってもらおう」と考えていた。
「まずは、翁の意識が戻ったことは良いことです。次は必ず皆を起こしてくださいませ」
と去来は、言った。
次の日の夜、其角は所要で家に帰っていたが、芭蕉が起きたため一同を呼んで。
「皆々様。誠に最後までご迷惑をお掛けして申し訳ございません。ごふぉ…。支考や。筆と紙を持ってきてくれ」
いよいよ辞世の句でもと一同は固唾を飲んだ。
「まずは皆々様に今生の別れを申し上げる。皆々様のおかげで、私の一生は、大変面白うございました。また俳諧の種も諸国に広まり愛好者も増え、ひとえに皆々様のおかげと存じております。支考筆を。う…」
「私が代筆しますので。何を書けばよろしいですか」
「いや、私が書こう。起こしてくれ。『御先に立ち候段残念に申し召さるべく候。如何様とも又衛門便りになされ、御年寄られ、御心静かに御臨終なさるべく候。ここに至って…ぐふぉ、申し上ぐる事御座なく候。市兵へ…。』ごほごほ」
「私がやはり代筆致します」
芭蕉は支考の申出を断り、
「十月十日松尾半左門衛門様、桃青、新蔵は殊に骨折られ忝く候」伊賀の兄宛を書き上げた後、
「では、次は私のものの肩身分けじゃ。これは、支考が書いてくれ」
「承ります」支考は筆を取ると、芭蕉はほそぼそとした声で、
「一つ、三日月記伊賀に有り、一つ、…発句の書付同断、一つ、新式 是は杉風へ遣わされるべく候。落字これ有り候間、本写しを改め校せらるべく候。…」形見分けの後は、甥と娘他宛を書かせ、
「次郎兵衛よ。くれぐれもまさとおふうのことよろしく頼むぞ。困ったことができたら好斉老を頼るのだぞ」そして江戸のまとめ役の杉風宛、弟子達宛に遺書を書かせた。
「ごほごほ…。門人方、其角はこちらへ登り、嵐雪を初めとして、残らず御心得なさざるべく候。元禄七年十月。支考や、遺書を見せてくれ」
「はい。」
「うむ。筆を…ばせを。最後は花押を…」
「はい。辞世の句は如何致しましょうか」去来は聞いた。
「少し疲れた。休ませてくれ」
「お休み下さいませ」去来は、芭蕉と話が出来、えらく感動したが、辞世の句をよまれなかったが気になった。
